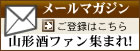山形讃香とは
共同銘柄だが、同一酒ではない。蔵元の個性が生きる夢のブランド。
昭和59年。壮大な構想が知事の提言により動き出していた。目的は本県を代表する大吟醸酒の商品化。
何より興味深いのが県産の大吟醸酒の中から選抜された、一定水準以上の数種を、共同銘柄『山形讃香』として売り出そうという点。
同一酒ではなく、各蔵元の個性もそのまま生かす...といった、まさに夢のブランドの実現であった。
酒造組合連合会はまず各蔵元(会員)に主旨を伝え、第一回目の大吟醸酒審査会の実施を告知。
参加は、既に大吟醸酒を造っている蔵元を中心に20社であった。
香味重視の厳しい審査の結果、約3割の7種が合格し、これらは昭和60年10月に、共同銘柄『山形讃香』としてデビューを果たした。
審査会側の熱意が伝わり金賞受賞数も格段に増加。
年に数回行われる審査会の厳格さは有名で、当初は「大吟醸の特質上、出品できる蔵元が限られるのではないか」「お互いの酒に
優劣をつけるのは反対」との反発もあった。
しかし審査会側の「県産酒の最高峰を!」との熱意が理解され始めると、良い酒を造れば『山形讃香』として認められる...といった理解や、吟醸酒造りに新規参入する蔵元も出てくるなど、前向きな競争意識が業界全体に波及していった。
思えばこれが、後の純米吟醸酒DEWA33誕生への布石でもあった。
「寡黙だが人の倍は努力」するのが山形県人。静かな闘志はやがて、技術力として実を結ぶことになる。
その証拠に『山形讃香』誕生以降の昭和61年頃から、東北や全国の鑑評会における本県の金賞受賞数が飛躍的に増加。現在では、金賞多数の常連県として全国的にも有名だ。
妥協を許さない真摯な姿勢、「最高峰」へのこだわり。
しかし過去に一度、頭の痛い出来事もあった。歳暮商戦を前に首都圏などの百貨店で欠品をさせてしまう。
原因は、直前の審査会での合格がゼロだったことによる出荷の制限。
「通常の大吟醸酒レベルでは何ら問題ない。しかし、あくまでも県産酒の最高峰にこだわると...」とのプライドが下した、当然の決断だった。
──かたくななまでに厳しく、そして崇高とも思えるこだわり。
最高峰という言葉がただの飾りではないことを、一杯の『山形讃香』が清らかに語っている。
|




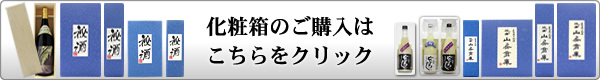








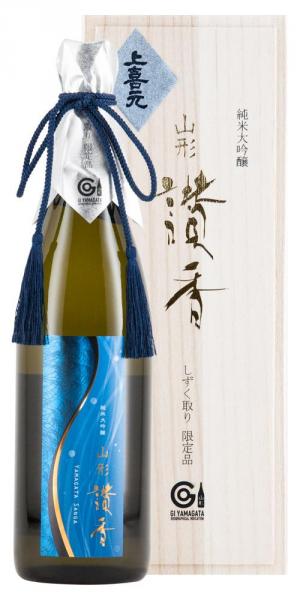

















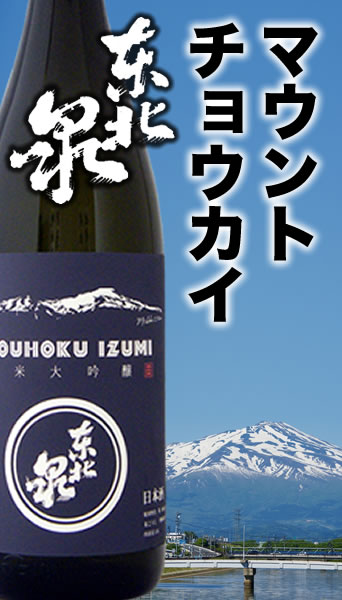 コストパフォーマンス抜群! 東北泉の自信作です
コストパフォーマンス抜群! 東北泉の自信作です
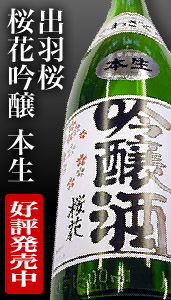 華やかでフルーティな香りとキレ。出羽桜を代表する吟醸酒。
華やかでフルーティな香りとキレ。出羽桜を代表する吟醸酒。

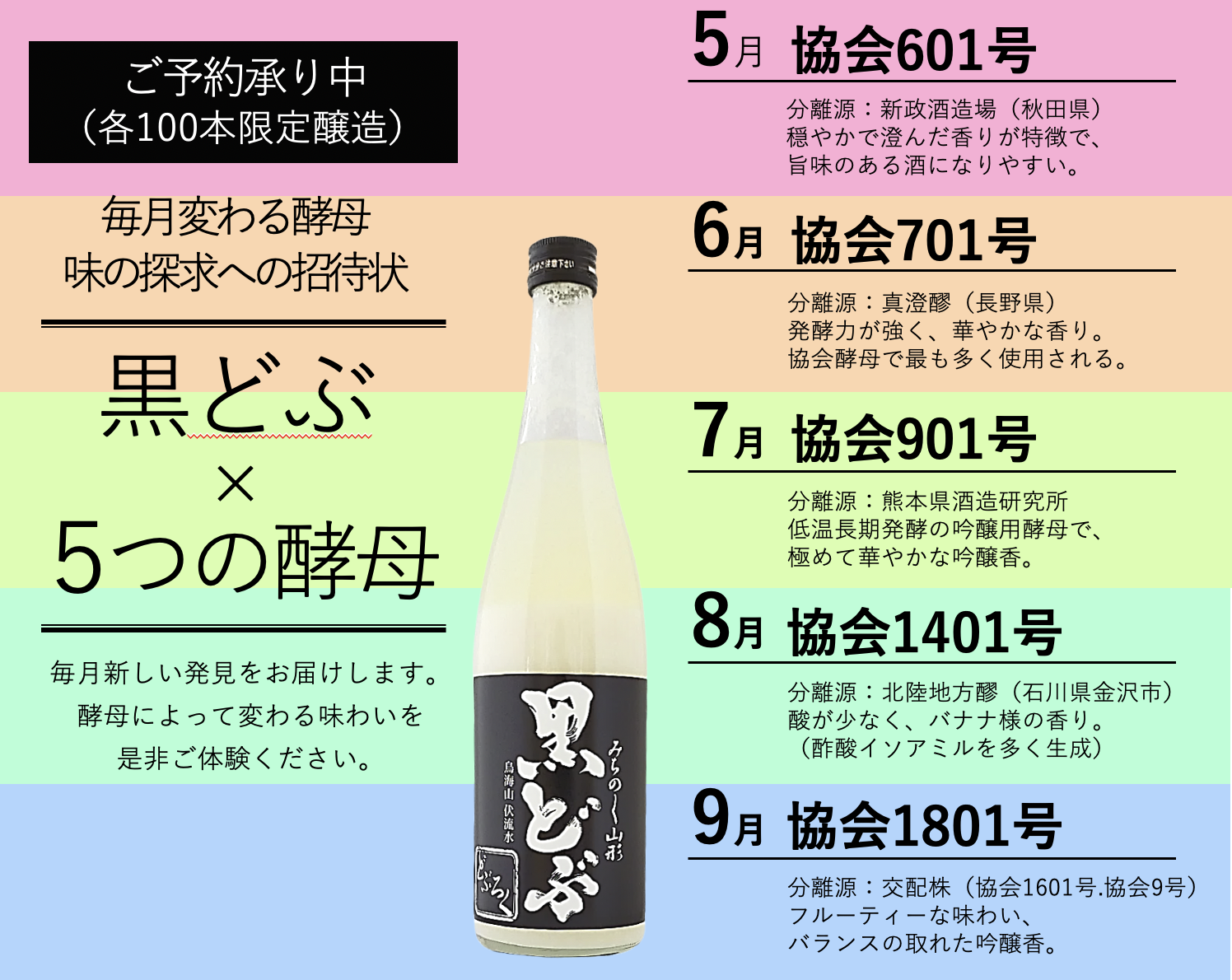



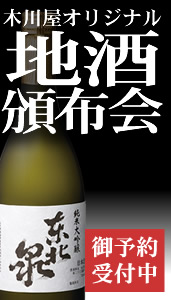 お陰様で27年目
お陰様で27年目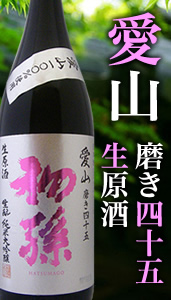 ジューシーな米の旨味が美味しい芳醇生原酒
ジューシーな米の旨味が美味しい芳醇生原酒 シュワッとしたガス感とジューシーな旨味をお楽しみください
シュワッとしたガス感とジューシーな旨味をお楽しみください
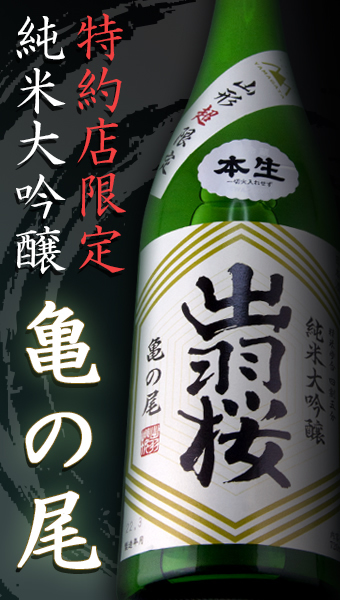 山形県内の厳選された10店のみ取り扱い可能な酒
山形県内の厳選された10店のみ取り扱い可能な酒
 酒田醗酵渾身の大吟醸どぶろくの熟成限定版
酒田醗酵渾身の大吟醸どぶろくの熟成限定版
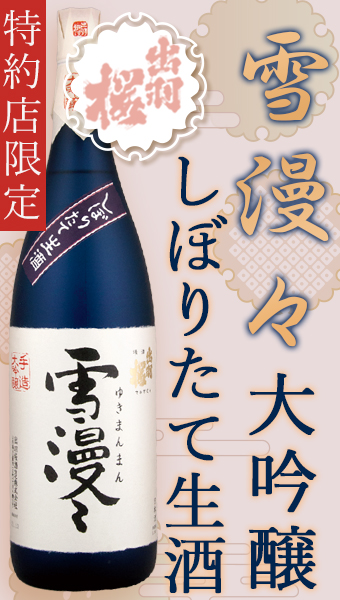 極々限られた特約店のみが取り扱いを許された酒
極々限られた特約店のみが取り扱いを許された酒
















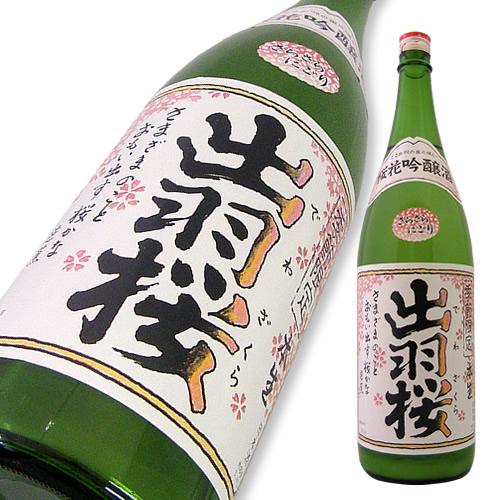

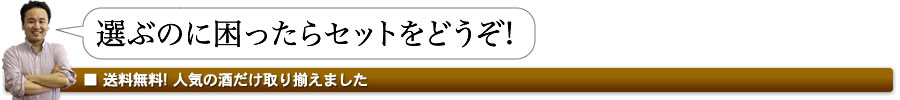













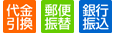
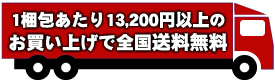
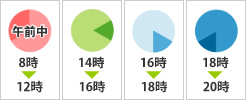




 の部分は新橋本店(ネット通販部門)の定休日です。
の部分は新橋本店(ネット通販部門)の定休日です。